犬は噛む生き物と言いますが、大事な家具や気に入っている家具を噛まれてボロボロにされるとショックを受けてしまいますよね。
怒ったり対策をとってもなかなか噛むのを止めてくれず、困っているという飼い主さんも多いのではないでしょうか。
そこで今回は「犬が家具を噛む理由」や「家具を噛ませない対策5つ」をご紹介します。
噛み癖対策でよく耳にする「スプレー」や「アルミホイル」を使う注意点もお話していきますのでぜひ最後までご覧ください。
犬が家具を噛むのはなぜ?噛む理由4つ
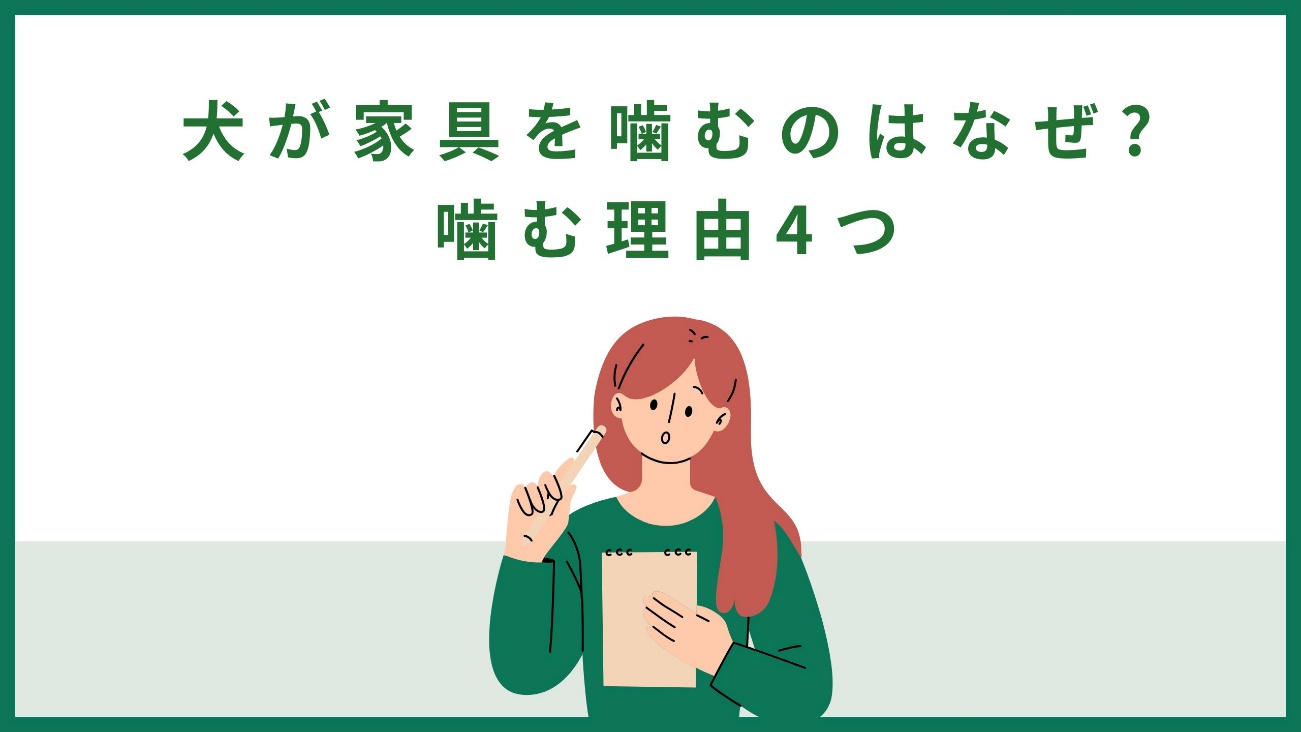
そもそも犬はなぜ家具を噛むのでしょうか。
考えられる理由を4つご紹介します。
▼「犬が家具を噛む理由4つ」
①「探索活動」
②「遊びたい」
③「ストレス解消のため」
④「歯がムズムズする」
①「探索活動」
犬が気になった物を噛んだり舐めたり匂いを嗅いだりするのは探索行動の一種で通常の行動です。
子犬のときには頻繁に見られる行動ですが、成長するにつれて収まることが多いです。
ただ犬によっては大人になってもかじる癖が抜けず、生涯噛んで探索する犬もいます。
②「遊びたい」
家具をおもちゃに見立てて遊んでいる可能性もあります。
家具を噛み締めると満足感が得られますし、かじると味や匂いも変わるので犬の興味を引きやすいです。
また、犬歯や臼歯で噛んだ時にしっかりと弾力が感じられると、より犬の本能がかき立てられるので夢中になって遊びます。
③「ストレス解消のため」
恐怖や不安を感じるとその気持ちを紛らわせようと物を噛んでしまうことがあります。
また、運動時間や運動強度が足りない場合も、有り余ったエネルギーを発散させようと物を噛むことがあります。
④「歯がムズムズする」
歯が生え変わる時期の子犬は、歯のムズ付きを解消するために物を噛みたい欲求が強くなります。
「家具を噛むのを止めさせるには?」噛み癖対策5つ
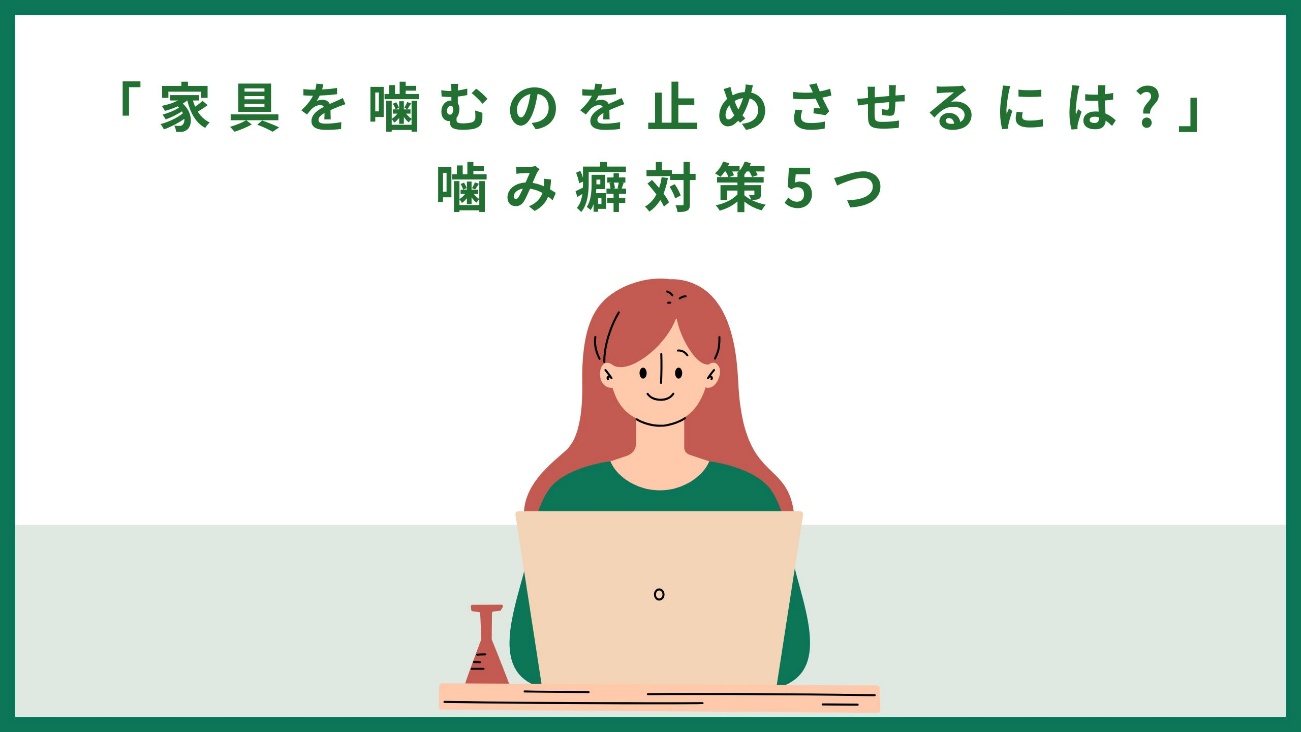
では、犬に家具を噛むのを止めてもらうには、どんな対策を取ればよいのでしょうか。
考えられる対策を5つご紹介します。
▼犬に家具を噛まれないための5つの対策
①「家具を移動させる」
②「家具を噛まれないようにガードする」
③「噛んでも良い物を与える」
④「家具を噛むのを邪魔する」
⑤「体力を発散させる」
①「家具を移動させる」
一番シンプルな方法は家具を移動させてしまうことです。
移動できない物ももちろんあると思いますが、犬が過ごす空間になくてもいい家具は別の場所に移動させましょう。
犬の行動を変えたり対策を取るのは大変なので、生活動線の見直しや片付けなど人側の努力で変えられるものは変えてしまいましょう。
②「家具を噛まれないようにガードする」
家具の前や家具に向かうルートの途中に柵やゲートを設置して、家具に犬が近づけないようにしましょう。
もし柵やゲートを設置するのするのが難しい場合は、よくかじる部分にタオルなどを巻いてガードしましょう。
噛んだ部分が取れたり削れたりすると、犬が楽しさを感じて余計にかじり続けるので、物理的に犬がかじれない環境をつくりましょう。
③「噛んでも良い物を与える」
家具を噛むのを止めさせたい場合は同時に噛んでも良い物を与えましょう。
使い古しのタオルやスリッパなどでも良いですが、新品の物と古い物の区別が犬にはつかないので、できれば犬用のおもちゃを用意しましょう。
「引っ張りっこ用のロープ」「コング」「ぬいぐるみ」などがオススメです。
おもちゃが1種類だけだったり常に出しっぱなしの環境だと犬が飽きてしまうこともあるので、日替わりで遊べる数(5~7個)を用意し、遊ばないときは閉まっておきましょう。
ひづめなどは長時間噛めますが、硬すぎて歯が折れる可能性もあるので、噛ませるものの硬さは注意して選びましょう。
④「家具を噛むのを邪魔する」
犬が家具を噛んでいる所を見つけたら、家具と犬の間に入ったり声をかけて家具を噛むのを中断させましょう。
中断させた後に噛んでいいおもちゃを与えて一緒に遊んであげましょう。
何度か繰り返すと「家具を噛んでいるといつも邪魔される」「でもおもちゃを噛んでいると一緒に遊んでくれる」と学習して、おもちゃの方を積極的に噛むようになります。
家具を噛むのを中断させるときは、大声を出したり怒鳴りつけたりしないようにしましょう。
犬は「家具を噛んではいけない」という概念がないので、怒られた理由がわからず怯えたり隠れて家具を噛むようになるので、静かに中断させましょう。
⑤「体力を発散させる」
遊びや運動、散歩の時間が少ないと犬が欲求不満になり、家具を噛んでしまうことがあります。
犬が家具を噛めない対策を取ったら、愛犬の生活も見直してみましょう。
散歩や全身運動の時間にプラスして知育のおもちゃやノーズワーク(嗅覚を使った遊び)で頭も使って体力を発散させましょう。
逆に体力が有り余っていたり、欲求が解消できずストレスが溜まっている状態だと普段家具を噛まない犬も噛み始めることがあるので、普段からストレスが溜まっていないか気を配ってあげましょう。
犬が家具を噛まないように「スプレー」「ワサビ」「アルミホイル」は効果がある?
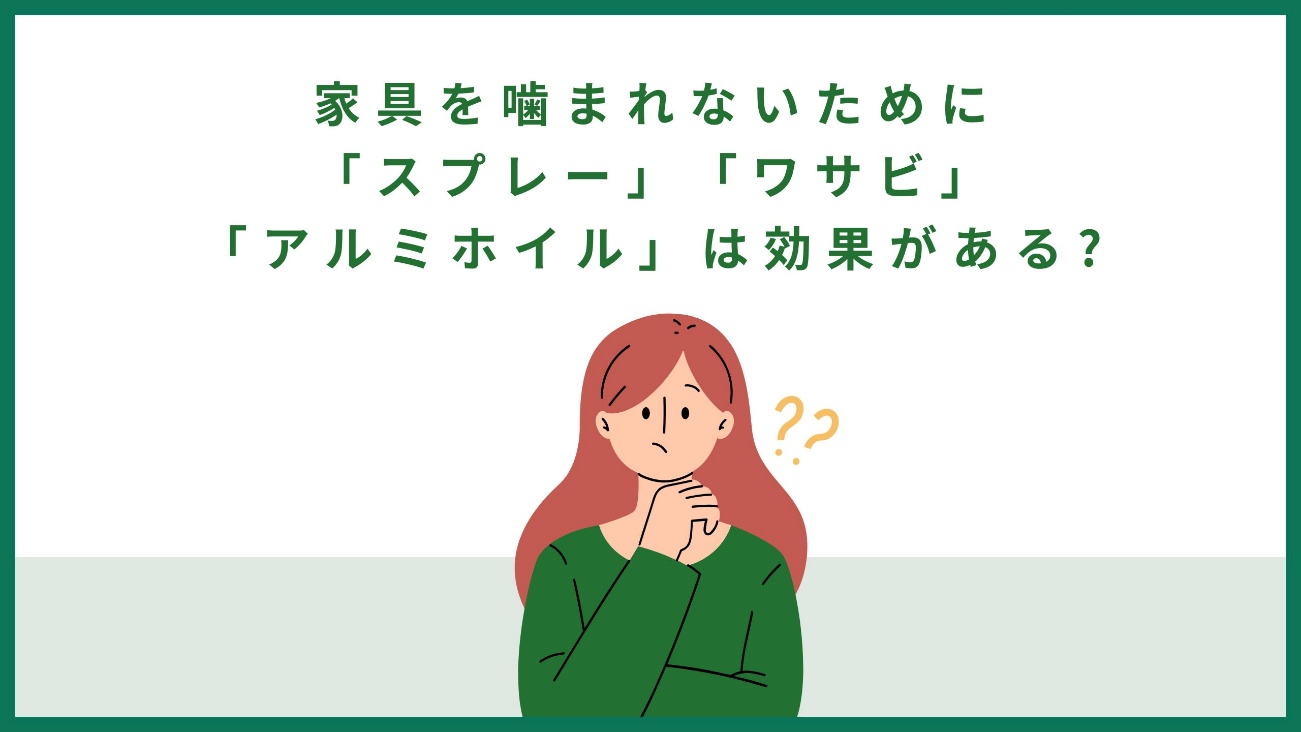
犬が家具を噛まないようにする対策として「かじり防止スプレー」「アルミホイル」「ワサビ」などが紹介されていることがあります。
こういった対策は実際に効果があるのでしょうか?
試してみて実際に効果があった方もいらっしゃるとは思いますが、犬の安全面や効果面から見ると、注意が必要なポイントがあるのでご紹介します。
▼対策の注意点
・「アルミホイル」は誤飲の危険がある
・「ワサビ」は胃腸に刺激を与える可能性がある
・「スプレー」は慣れると効果がなくなる
・「アルミホイル」は誤飲の危険がある
犬が噛む部分にアルミホイルを巻くと嫌な感触がするので噛むのをやめるという方法が紹介されています。
噛むのを辞める犬もいるかもしれませんが、アルミホイルをかじって誤飲する危険があるので、あまりオススメではありません。
飲み込んだ量が多ければ腸閉塞の危険がありますし、アルミホイルの尖った部分が刺激になり炎症や嘔吐を引き起こす可能性があります。
・「ワサビ」は胃腸に刺激を与える可能性がある
犬が噛む部分にワサビを塗る方法も紹介されていることがあります。
ですが舐めてしまうと、ワサビに含まれる辛味成分が胃腸障害を起こす可能性があります。
刺激が強い食材なので、少量であってもしつけには使わないことをオススメします。
・「スプレー」は慣れると効果がなくなる
犬に噛んでほしくない物にしつけスプレーを吹きかける方法も紹介されています。
天然成分を利用して犬が口にしても問題ないように作ってありますが、噛まなくなる効果は犬によって異なります。
犬にとって不快な味がする場合が多いですが、犬によっては不快に感じなかったり何度も使ううちに慣れてしまう場合もあります。
また時間が立つと揮発で効果が薄れてしまうので、こまめに吹きかける必要が出てきます。
そのため、スプレーだけでなく「家具を移動させる」「家具を柵で囲う」のように別の対策も一緒に取り入れるとよいでしょう。

犬が家具を噛む理由は単に遊びというだけでなくストレスや不安からきていることもあります。
その場合、無理やり止めさせようとすると、家具を噛まなくても別のいたずらを始めたり、自分自身を噛むといった自傷行為が始まることもあります。
ただ止めさせるのではなく「噛んでも良い物を与える」「犬の生活を見直す」といった対応も同時に行うことが大切です。
<参考URL>
【調査レポート】イヌパシー|イヌの本能に寄り添うデータ解析を実施!客観的データで「噛むこと」の価値を示し、飼い主への新しい習慣機会を提供
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000035795.html
<参考書籍>
・動物看護のための動物行動学
<画像元>
Canva
・(元)認定動物看護師
・一般社団法人日本小動物獣医師会 動物診療助手
やんちゃなミックス犬とおっとりトイプードルと暮らす。
大学在学中に「病気になる前の予防が一番大事」と気づき、
ペットフードやペットサプリメントの会社に就職。
「食」に関するさまざまな知識を身につける。
愛犬を亡くしたときに
「もっと色んな情報を知っておけば」と感じた後悔を
「他の飼い主さんにはさせたくない」との思いから、
ライター活動を開始。
「勉強になった・信頼・わかりやすい」を目標に情報を発信しています。
最新記事 by 伊藤さん (全て見る)
- 「こんな言葉を言われたら要注意」子犬探しで気をつけてほしいワード5選 - 2026年1月19日
- 「犬はストレスがたまるとどうなる?」ストレスサインの種類と行動変化、解消法をご紹介 - 2026年1月5日
- 「愛犬が散歩中に動かなくなるのはわがまま?」歩かない、違う方向に行く理由と対処法を解説 - 2025年12月30日
- 「犬にレインコートはいる?いらない?」レインコートの選び方や慣らすポイントをご紹介 - 2025年12月22日
- 「アウトドアやキャンプは危険がいっぱい?!」犬が刺されやすい虫5選とその対処法をご紹介 - 2025年12月15日


